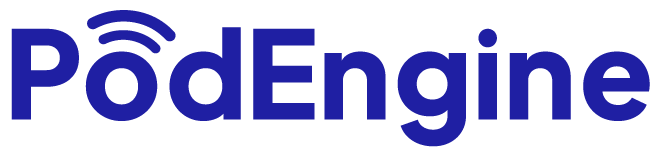by 田舎坊主 森田良恒
田舎坊主の読み聞かせ法話 田舎坊主が今まで出版した本の読み聞かせです 和歌山県紀の川市に住む、とある田舎坊主がお届けする独り言ー もしこれがあなたの心に届けば、そこではじめて「法話」となるのかもしれません。 人には何が大事か、そして生きることの幸せを考えてみませんか。
Language
🇯🇵
Publishing Since
1/8/2023
Email Addresses
0 available
Phone Numbers
0 available

June 27, 2024
<p>仏事に関しては各宗派に違いがあります。</p> <p>さらには同じ宗派でも地域によっても違いがあります。</p> <p>これは仏事がそれぞれの地域の特色や歴代の住職の考え方などが大きく影響し、文化の一部として慣習化したものが少なくないからでしょう。</p> <p>たとえば同じ宗派であっても、かつては土葬と火葬が共存していたため、それぞれの葬送の仕方を受け入れないところがありました。</p> <p>土葬埋葬は亡きがらを捨てるようで、しかもその上に重い土をかけるのがかわいそうだといい、一方は火葬は熱そうだからいやだといいます。</p> <p>また、葬式を済ませて中陰の間は仏壇を閉じるところと、開けたままにしておくところがあります。</p> <p>当田舎寺では仏壇を閉めないようにお話ししています。</p> <p>しかし親類縁者から閉めるようにいわれることが多いのか、この件についてはよく聞かれることでもあります。</p> <p>仏壇は本来ご本尊を安置するものです。</p> <p>ですからご本尊の安置されていない仏壇はあくまでもご先祖の位牌置き場ということになります。</p> <p>もともと仏壇を家に置くようになったのは、ご先祖供養のためわざわざお寺へ行かなくてもいいように、いわばミニお寺を家の中に置く感覚で普及してきたと考えられます。</p> <p>そのなかに方便としてご先祖の位牌を同居させているのが現在の仏壇のありようなのです。</p> <p>その証拠に仏壇をよく見ると実際には位牌置き場というところはありません。</p> <p>本尊を安置している須弥壇という高台に至る階段模様の段々上に位牌を置いているのが現状なのです。</p> <p>あくまでも仏壇の主人はご本尊なのです。</p> <p>特別に壇をしつらえお祀りされるのは、亡くなって間もないご先祖の魂が、名残なく迷うことなく黄泉の国へ旅立ってほしいと願い、大切なご本尊に手を合わせ、護られ、導かれたいと思うからであります。</p> <p>にもかかわらず、ご本尊のいます仏壇が閉じられていたのでは、祈念が通じないのではないかと思うのです。</p> <p>ですから私は中陰の間も仏壇を開けておくようにお話しします。</p> <p>私の暮らす地域は二十数年前までは土葬が中心でした。</p> <p>その後、多くの反対意見も出るなか、近くに火葬場もできたので、それからはすべて火葬に替わりました。</p> <p>火葬の始まりは、2500年前、お釈迦さまはインド北部クシナガラで生涯を終え荼毘に付されたところからです。</p> <p>火葬にされたお骨は世界七カ国に分骨され、それぞれガラス製の骨壺に納められ、それをお祀りする場所として仏舎利塔が建てられました。</p> <p>これがストゥーパとよばれ、漢訳され現在の「卒塔婆」になったのです。</p> <p>お骨になったということは、すべてが自然に還ったことであります。</p> <p>すべてが自然に還った燃え残りとしてのお骨でさえ、あまりにも偉大なお釈迦さまのものであればこそ、貴重なガラスの器に入れ、これを礼拝する対象としたのです。</p> <p>弘法大師ご入定のあと高野山を真言宗の根本霊場として完成させた真然大徳の御廟が修復された平成二年、、瑠璃色に焼かれた骨壺がそのまま掘り出されました。</p> <p>このことは全国紙にもカラーで報道されました。</p> <p>その骨壺はそのまま真然大徳の御遠忌で落慶された御廟に再び納められました。</p> <p>このようにこういった方々の骨壺はとても大切に扱われるものであることは言うまでもありません。</p> <p>しかし庶民の埋葬意識は少し違っていて、火葬してからもお骨を土に還すという観念で納骨される方がたくさんおられます。</p> <p>埋葬文化は「土に還る」を第一義とされていますので、骨壺に入ったままでは土に還れず成仏できないと思うのでしょう。そういう方々は骨壺を割りお骨を直接土にまく必要があると考えているのです。</p> <p>あるお宅の納骨供養の際、その親戚の長老らしき方が采配しだしました。</p> <p>「おい、骨壺からお骨を出して、その穴へ撒いて・・・」</p> <p>「壺を細かく割って、深いところに埋めて・・・」</p> <p> 私が口を挟むまもなく納骨は進んでいきました。</p> <p>「そのまえに、写経した用紙はあるか?」</p> <p>「それはお骨の下に敷くんや」</p> <p>「よっしゃあ、それでええわ」</p> <p>写経用紙の取り扱いまで指導したところで、</p> <p>「次は土をかけるんや、一鍬ずつでええで」</p> <p>と、参列者を順番に名指ししながら最後まで取り仕切ってくれました。</p> <p>その方が納骨に詳しいことは間違いないのですが、骨壺を割る必要がないことを話す暇も田舎坊主にはありませんでした。</p> <p>それで安心が得られるのでしたら、またそれも善き哉。</p> <p>合掌</p> --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/pgsvmgddld/message

June 20, 2024
<p>法事とは亡き人のご供養をすることです。</p> <p>葬式のあと初七日から満中陰までの七回と、百日忌、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌とあります。</p> <p>すべてを勤めるとして五十回忌まで20回の法事をすることになります(二十五回忌、四十三回忌、四十七回忌を加えて23回とするところもあります)。</p> <p>明治初めころまで庶民は字が読めずお経をあげることができなかったため、その都度、お寺の本堂で僧侶にお経をあげてもらっていました。追善供養したいという風習により、やがて各家に仏壇が祀られるようになって自宅で法事をするようになったのでしょう。</p> <p>仏壇の前で法事を勤めることもありますが、この辺りの田舎ではほとんど仏壇から位牌を取り出します。そして床の間にあらたに座敷机などで祭壇をもうけて法事をします。</p> <p>祭壇の上には正面に位牌を置き、花瓶、線香立て、花立て、ロウソク立てなどを並べます。果物やお菓子、季節の花や故人の好物だった品々もたくさん供えられます。</p> <p>法事とは本来、亡くなって自らお経をあげることができなくなったご先祖さまに代わって僧侶を招き、遺族とともに、本尊にお経をあげ功徳を積むことなのです。</p> <p>「追善」という言葉も、「善き功徳の追加」であって、法事同様、亡くなって功徳を積むことができなくなったご先祖に代わり、親類縁者が一堂に会して、最も功徳があるとされる読経をご本尊にお供えすることなのです。</p> <p>ですから、一番大事なことは仏壇の中の本尊やまたは本尊に代わる掛け軸を、祭壇の正面の奥に安置することなのです。</p> <p>当寺の法事では仏前勤行次第の冊子を渡し、一緒に経をお唱えするようにすすめますが、参加者が声をそろえてお唱えしてくれたときなどは、</p> <p>「今日のご先祖さまが皆さんの後ろの末席にいて『みんなで拝んでくれてありがとう。わたしの代わりに拝んでくれてありがとう』と、お礼を言ってると思いますよ」と、私は話します。</p> <p>要するに、あくまでもメインは当家のご本尊なのです。</p> <p>しかしほとんどの家では位牌がメインのように中心、正面に置かれています。ご本尊は二の次のようになってしまっているのです。その上、床の間の置物がそのまま置かれていて、本尊代わりのようになっていることも多いのです。</p> <p>その置物が、あるときは鷹の剥製だったり、鮭をくわえた熊だったり、あるときは徳利をもったタヌキがヘソを出して立っていたりすることもありました。</p> <p>私は同じタヌキでも、楊子(ようじ)をくわえた紋次郎タヌキ(昭和47年からテレビ放映された「木枯らし紋次郎」を真似た置物)にもお経をあげたこともあります。</p> <p>合掌</p> --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/pgsvmgddld/message

June 13, 2024
<p>法事に必要な時間は約1時間です。</p> <p>その内訳はおおよそ読経が25分から30分、法話が10分、そのあとお墓参りをして終了となります。</p> <p>読経の最後には、般若心経や諸真言など法事に来られる年齢の方々なら比較的なじんでおられるお経を中心に「仏前勤行次第」という手づくりの小冊子を配って、みんなでお唱えします。</p> <p>こんな方法にしたのは、昭和52年ころ法事にお参りして読経をしているときのことがきっかけでした。</p> <p>当時は、法事に招かれる親類縁者のほとんどがミカン農家でした。</p> <p>その人たちがそれぞれ農作業の進み具合や消毒、摘果、実のなり具合などを、法事最中、小声ではあるのですが真剣に話し出して、うるさいのです。</p> <p>坊主の後ろに座ってただ訳の分からないお経を聞いているのが、ある意味苦痛だったのでしょう。</p> <p>あるいは小坊主に遠慮は無用でお経の最中であろうとそれほど失礼とは思われなかったのだと思います。</p> <p>私が至らないことも大きな原因ですが、とにかくうるさいのです。</p> <p>そこでお経の最中の口封じのため考えたのが、昔ですから、鉄筆を使ったガリ版印刷で「仏前勤行次第」をつくり、みんなで一緒にお唱えすることだったのです。</p> <p>お経の後半で「ご一緒にお唱えください」と声かけをし、参列者全員で読経唱和を始めたところ、まずまず評判よく受け入れられました。しかも案外効果は早く出てきて、それ以来、読経中の会話は全くといっていいほどなくなりました。</p> <p>ところが困ったことも起きてきました。それは「仏前勤行次第」の冊子をほしいという人が増えてきたのです。</p> <p>しかしなんといっても当時はコピー機もワープロもましてやパソコンもありません。鉄筆で油紙に手書きし、インクを染みこませたロールを一回一回、押し転がしながら刷り上げ、一冊ずつ製本するのですから、増刷が大変なことはいうまでもありません。</p> <p>当初はお断りをし、お貸しするだけにしていたのですが、なぜか法事のたびに冊数が減っていくのです。</p> <p>そうです。内緒で持って帰られるのです。</p> <p>そこで思いついたのが冊子ではなくB4用紙一枚に「仏前勤行次第」すべてを書き込んだものをつくり、ほしい方にはそちらを差し上げることにしたのです。</p> <p>しかしそれでも、</p> <p>「冊子本の方が字が大きいから見やすいので、それがほしい」と、いいだす人もありました。</p> <p>そんなこともあったので、さらに思い切って、約400部つくって檀家皆さまに一冊ずつ差し上げることにしたのです。</p> <p>私は法事の時、よく言うことがあります。</p> <p>それは「寺から里へ」ということです。</p> <p>かつては、農家でとれた野菜やミカンなどをお寺へもっていくのはごく普通のことで当たり前のような行為でした。ですから「里から寺へ」は当たり前のことと言えます。</p> <p>反対に、お寺のお供え物やいただきものなどを檀家さんに配るようなことはまずありません。</p> <p>ですから「寺から里へ」という言葉は「めったにない」という意味をもっています。</p> <p>しかしこの田舎寺では「仏前勤行次第」を無料で差し上げます。</p> <p>「寺から里へを実践する、めったにないお寺なんですよ」と、もったいぶって差し上げるんです。</p> <p>合掌</p> --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/pgsvmgddld/message
Pod Engine is not affiliated with, endorsed by, or officially connected with any of the podcasts displayed on this platform. We operate independently as a podcast discovery and analytics service.
All podcast artwork, thumbnails, and content displayed on this page are the property of their respective owners and are protected by applicable copyright laws. This includes, but is not limited to, podcast cover art, episode artwork, show descriptions, episode titles, transcripts, audio snippets, and any other content originating from the podcast creators or their licensors.
We display this content under fair use principles and/or implied license for the purpose of podcast discovery, information, and commentary. We make no claim of ownership over any podcast content, artwork, or related materials shown on this platform. All trademarks, service marks, and trade names are the property of their respective owners.
While we strive to ensure all content usage is properly authorized, if you are a rights holder and believe your content is being used inappropriately or without proper authorization, please contact us immediately at [email protected] for prompt review and appropriate action, which may include content removal or proper attribution.
By accessing and using this platform, you acknowledge and agree to respect all applicable copyright laws and intellectual property rights of content owners. Any unauthorized reproduction, distribution, or commercial use of the content displayed on this platform is strictly prohibited.